2021年、NFTの全世界での売上は2.5兆円を超えたそうである*1。その前年が100億円程度だったことを考えると、凄まじい成長である。それがどれくらいの規模かをイメージするのに、日本のインターネットメディア広告費を思い浮かべるといいかもしれない。100億円規模だったのは1998年、2兆円を超えるのは2019年だ。全世界と日本とでは同一条件の比較とはいえないが、それでも、あるところでは21年かかった成長を、わずか1年でやってのけたマーケットがあったのだから、突如のデジタルゴールドラッシュに人々が沸き立つのも無理からぬ事だろう。
しかし、そんな話を聞けば聞くほど、胡散臭さに身構えてしまうのが心理というものだ。メディア業界にはまだ投資家やアーティストやゲームデベロッパーのように泡のうえで踊る順番がまわってきていないから、輪には加わらずにクールな批評家でいるほうが賢明のようにも思える。それに、ブロックチェーンやクリプトやスマートコントラクトという言葉だってまだ人口に膾炙したとも言えないなか、NFTやDeFiやGameFiやDAOといった新語が束になって「Web3」と名乗られても意味がわからないと感じるのも当然だろう。どれだけ「なぜWeb3が重要なのか?」*2と声高に叫ばれても、第三者の視点を欠いたステートメントは「いやそれはあなたにとって重要だからですよね」という感想しか呼び起こさないし、バズワードを褒めそやすほどメディアはお人好しではない。となれば、イーロン・マスク氏の「どこかにWeb3を見た人はいますか? 私には見つけられません」*3という皮肉にも与したくなってくるというものだ。
と、これだけ書けばエクスキューズとして十分だろう。
私が実際に感じていることはこうだ。
それでもWeb3はおもしろい。
想像するに、メディア業界の読者が知りたいのはこういうことではないだろうか。Web3はコンテンツにとって本物の黄金時代をもたらすものなのか、それとも、かつてマーク・トウェインがアメリカの拝金主義を揶揄した言葉に倣えば、偽物の金ぴか時代に過ぎないのか? 私が試みようとするのは、流行語をなるべく使わずに、古くからあるよく知られた言葉でそれを吟味することだ。
オーナーシップの革命とデジタル希少性
そう考えてすぐ、最良のテクストに思い当たった。未来学者のエイミー・ウェブが創業したFTI(Future Today Institute)の年間レポートである。
「Web3」というキーワードがとりあげられた最初の年である2019年の資料「2020 TREND REPORT FOR ENTERTAINMENT, MEDIA & TECHNOLOGY」からいくつか引いてみたい。

世界最大のデジタルジャーナリスト協会ONAの基調講演で公開されたこの資料は、特にメディアやコンテンツに関わる人に向けられた内容となっている。
(Web3は)コンテンツがどのようにキュレーションされ、消費されるかというインセンティブ構造を、個々の編集者、スマートなアルゴリズム、そしてコンテンツに投票して対価を得る膨大なユーザーベースへとシフトさせています。これは、オンラインゲーム、ファッション、小売、観光、自動車メーカー、さらには2020年の政治キャンペーンに携わる人々など、さまざまな業界に影響を与えます。(p.135「118 Decentralized Content Platforms」より)
配信チャネルは、一握りのプレイヤーが市場を支配する「勝者総取り」のモデルが一般的です。Comcast、AT&T、YouTube、Vimeo、Soundcloud、Spotifyなどがその例です。これらの企業がなくなることは考えにくいですが、タレントや視聴者がより優れた機能(価格モデル、レベニューシェア、IP保護)を持つ他のプラットフォームに一斉に移動すれば、これらの企業は市場のリーダーとしての地位を失うかもしれません。(p.132「116 Tokenizing Assets」より)
ニュースやメディアは、かつて1980年代にCompuServeのニュースサービスが採用した経済モデルを見直す機会を得ています。これは、読者が記事を見るたびにお金を払い、画像には追加料金を払うというニュース構造でした。最終的には、無料で質の高いジャーナリズムが増えたことや、GoogleやAOLなどの無料検索サービスの登場により、このサービスは失敗に終わりました。(p.133「117 Tokens for Smart Royalties and Freelancers」より)
翻訳と太字は筆者。さて、これら3つの内容は、次のように言い換えられる。
- コンテンツ流通の主導権がユーザーにシフトすること
- いま覇権を握っているプラットフォームが力を失う可能性があること
- メディアには課金をともなうビジネスモデルを再考する機会が生じること
いまから2年以上も前の提言がここにきて確信の度合いをさらに高めているのは、NFTとそれらを扱うWeb3アプリの普及に加速がついたことによって、オーナーシップの革命にリアリティが出てきたからだ。エヴァンジェリストはWeb3の特徴を「分散型」という言葉で説明し、技術者は「コンポーザビリティ」という言葉で説明するが、いちユーザーがもっとも強くその変化を感じられるのは「オーナーシップ」とそれをめぐる動機の変化である。
オーナーシップが生じる技術的な裏付けは本稿では省き、その動機の変化について説明する。それが何によってもたらされるか一言でいうと、デジタル希少性である。限られたものだからほしい、珍しいものだからほしい、みんながもっていないからほしい、ほしいからほしい。つまりそういう心理のことで、現実では親しみのあるあの心理のことだ。
でもちょっと待ってほしい。複製コストが限りなく安いデジタルの世界に、人工的な希少性をデザインするというのはどういうことなのか。エドワード・スノーデン氏はイーサリアム共同創業者のギャビン・ウッド氏との対談で次のように苦言を呈した。*4
昔はお店に行って ゲームを購入していました。ゲームを所有し、ゲームをプレイする、それだけのことです。その後、サブスクリプションモデルのゲームが出てきます。ゲームを購入して、月々の料金を支払う、というようなものです。今、彼らがしていることの最終的な結果は、ポスト希少性の領域に人工的な希少性の感覚を注入していることです。これは、本質的に反社会的な衝動だと思います。(中略)このようなポスト希少性ドメインに、一部の投資家層の利益のためだけに、人工的な、不必要な希少性を注入することから、発展の弧を曲げようとしているのではないでしょうか。
スノーデン氏がこのときイメージしているのは、疲れて家に帰ってきてゲームで息抜きしようとしているユーザーなので、そう言いたくなる気持ちもわかる。しかし、話をコンテンツ全般に広げてみると、希少性のまったくない世界が碌なものにならなかった現実に思い至る。すべてのコンテンツが限りなく安価になると、まずアテンション・エコノミーが生じる。それを勝ち抜いた帝国が監視資本主義*5を完成させる。やがて世界は、誰でも手に入れられるが誰も欲しくないものであふれるようになり、ユーザー体験が貧しくなっていくのを誰にも止められなくなる。それが今おこっていることだ。
「ミントする」が市民権を得る日
オーナーシップの革命とデジタル希少性を手っ取り早く体験するにはどうすればいいか。値動きの激しいクリプトや、魅力のわからないアートや、興味の持てないゲームアイテムといったものを買わずに、メディア業界の人々がWeb3を感じられる具体的なサービスやコンテンツはあるか。私がお勧めしたいのは、Web3のPersonal Publishing Toolである「Mirror」である。
筆者個人は、Movable TypeではWebをパブリッシュする衝撃を、KDPではEPUBをパブリッシュする衝撃を体験したが、MirrorでNFTをパブリッシュする行為はそれに続く第三の衝撃となった。
なお、NFTとコロケーションを成すのはMint(鋳造する)という語なので、以後はそのように書く。なるべく流行語を使わないという方針があるものの、ゼロ年代前半にブログの普及と共に「エントリを書く」という言葉が普及したように、今後もしかして「ミントする」が市民権を得ることがあるかもしれないと思うからだ。
さて、Mirrorをめぐる体験だが、ジャーニーに沿って順番をつけると次のようになる。
- ENSでウォレットのアドレスに名前をつける
- Mirrorにウォレットを接続し、まずは普通にWeb記事をパブリッシュしてみる
- Mirrorで書かれた他のユーザーのNFT記事をミントし、コレクションに加える
- そのNFT記事のコレクターに自分の名前がリストされ、自分のMirrorにリンクされる
- etc.xyzで自分のプロフィールやコレクションを確認する
- OpenSeaにウォレットを接続し、保有するNFTをマーケットに出品できることを確認する
- Mirrorにウォレットを接続し、今度はNFT記事をミントしてみる
Mirrorでミントされた記事の具体例として、そして、内容的にも見るべきものがあるものとして、The Web3 Renaissance: A Golden Age for Content という記事を挙げる。
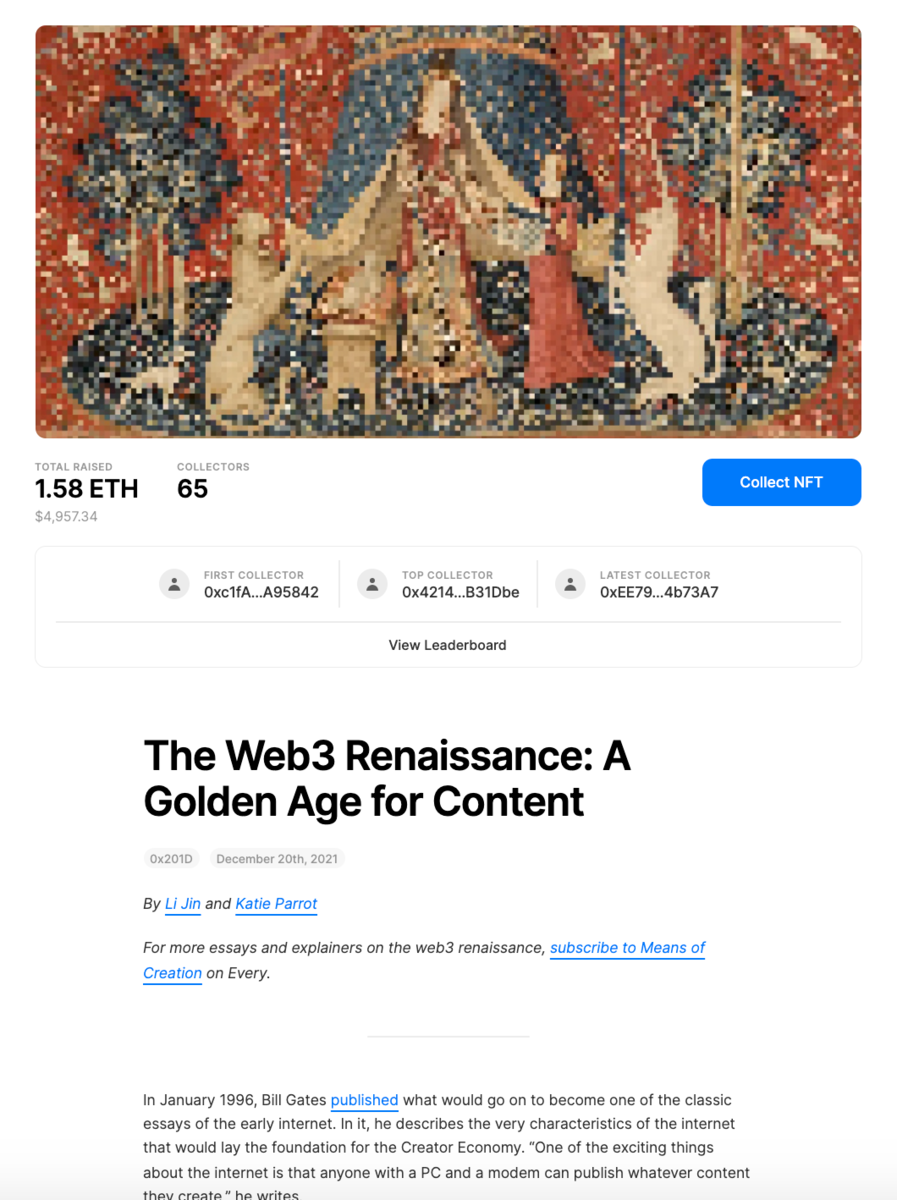
これらを通して実感が芽生えるのは、ウォレットによる認証と所有の世界観である。プラットフォームにIDやパスワードや個人情報やデータ資産を預けるようなやり方ではなく、ウォレットによって自分がそれを所有し管理するというWeb3の基本的な仕組みがわかってくるはずだ。
現実世界ではあたり前なのに、デジタル世界ではこれまでほとんど存在しなかったオーナーシップに目覚めてみると、自分のウォレットに何を加えたいか、またそれをどのようにデジタルのアイデンティティとして誇りたいか、といったことに関心が湧いてくる。そしてその近道は、自分もまた価値の創造のチェーンに列することにある。そこから実際に何かをミントするまでは、もうすぐである。
しかしおそらく、これを実際に試みた人は、何をするにも高額な手数料(これを「ガス代」と呼ぶ)がかかるイーサリアム上のサービス(ブロックチェーン上のアプリを「DApps」と呼ぶ)に、マスアダプションには程遠いという感想を持つかもしれない。ガス代については将来の解決策が示されているとはいえ、現状はまさにその通りである。
ところが、物を買いに行くには電車賃がかかり、同人誌を作るには印刷代がかかる現実のオーナーシップの世界を思い浮かべるとき、デジタル上のオーナーシップにも持ち出しが発生することには、奇妙な納得感があるのだ。もしそれを非難する場合には、無料のインターネットが何を代償にしていたか、立ち止まって思い出す必要がある。
筆者はふと、暖炉と本棚のことを連想する。

部屋を温めるエネルギーが石油や電気に変わってから、自宅に暖炉を構えるのはファッションになった。同様に、情報の取得という機能をデジタルメディアに譲ってから、立派な本棚をしつらえるのはファッションになった。それが悪いと言いたいのではない。逆である。暖房やインプットという機能が本質であるかのように錯覚するが、モノが纏っているファッション性もまた、欠かせない本質なのである。薪をくべない暖炉が部屋を温めることはないが、それは所有者の別の何かを満たすのだ。
なぜこのような例え話をするのかというと、Web3における情報は、このファッション性によっておもしろい展開を迎えるのではないかと思うからである。情報はフリーになりたがる *6が、ファッションはそうではない。希少性が肝心だからだ。だから人々は、豪華な革装の本や、背表紙に金文字が打ち込まれた百科事典を所有したがったのである。だとすれば、新しい方法でそれに応えることはできないか? Mirrorめぐる一連のサービスを体験すると、そうした可能性が思い浮かんでくる。
誰がその貨幣を鋳造するのか?
フランスのコンピュータ研究者に、フィリップ・ケオーがいる。90年代、アメリカの研究者や事業家がインターネットについて楽観的な未来予測をしたのに対し、ケオーは建設的な批判を行った。いま振り返ると、Web2.0の隘路を言い当てたのはケオーの方だったことがわかる。その氏が、1995年の論文「誰が未来のサイバー・エコノミーを統御するのか / Qui contrôlera la cyber-économie」にこんなことを書いている。
それは未来の経済における、いわば喉首の支配にかかわっている。いったいバーチャル貨幣はサイバー・スペースの金貨となるのか? 誰の統御のものとで、誰がその貨幣を鋳造するのか、それはまだわからない。*7
テーマは電子商取引についての問題点であり、その要素として「暗号、著作権、電子マネー」を挙げられている。逆に言えば、黎明期のインターネットはこの三要素が未整備のまま船出するしかなかったというわけで、それが後にマーク・アンドリーセンをして「インターネットの原罪*8」と呼ばせた。原罪という用語はややオーバーで、ストリーテリングの恣意性を感じてもしまうが、必要なものが欠けているという認識はインターネットの成立を間近で見ていた研究者や事業家の間では一般的なものだったようだ。だから当時、未来のサイバー・エコノミーの覇権を誰が握るのかについて、WIRED誌にこんなジョークが載ったという。「やがてダラー・ビル(ドル紙幣)からビル・ダラー(ビル・ゲイツのドル)になるだろう」。しかし、そうはならなかった。どんな企業にもそんなことはできなかった。ところが、サトシ・ナカモトがブロックチェーンとビットコインを発明して後、思いもよらなかった方法でその三要素を解決する道筋が見えてきたというわけだ。
さて、ケオーの問いに戻ろう。誰がその貨幣を鋳造するのか?
その貨幣を「トークン」と広義に読み替えたならば、驚くべきことに、それを鋳造するのは私たちなのである。私たちがミントし、私達が所有する。コンテンツに関わる者にとってのWeb3とは、簡単に言えばそういうものなのである。
Web2.0が普及期に入った2006年、タイム誌がパーソン・オブ・ザ・イヤーに「You」を選んだことが話題になったが、Web3が普及した暁には、再び私たちが時代の主役に選ばれることがあってもおかしくない。いや、それがコンテンツという王の帰還を意味するならば、もっと盛大に祝われてもいいはずだ。
Web3というのは、特級の輝きをもったバズワードである。でも、ものは見かけによらない(All the glitters is not gold)。表面がメッキに覆われているだけの話かもしれない。しかし、そのなかに本物の金が混じっていないとも限らない。だとすれば、それを見極め、精錬してインゴットにしてみせるのは私たちの腕次第であるはずだ。私はそれをおもしろがっている。
最後に、これを読んでWeb3が気になった方には、ぜひFTIのキークエスチョンに答えてみることをお勧めします。*9
私たちのビジネスモデルのどの部分が、Web3の進化がもたらすディスラプションに対して脆弱なのか? 将来のリスクを軽減するために、今何ができるか?
著者紹介

佐々木大輔(ささき・だいすけ)
スマートニュース 株式会社 執行役員事業担当
1980年、岩手県遠野市生まれ。株式会社インフォバーン、株式会社ライブドアからLINE株式会社を経て、2017年11月スマートニュース株式会社に入社。
Twitter:@sasakill
*1:$22 B. Spent on NFTs in 2021, Report Reveals – ARTnews.com
*2:Why Web3 Matters | Future, なぜWeb3が重要なのか
*3:https://twitter.com/elonmusk/status/1473165434518224896?ref_src=twsrc%5Etfw
*4:Gavin Wood & Edward Snowden December 3rd | DeData Conference - Talk Polkadot
*5:監視資本主義: 人類の未来を賭けた闘い(ショシャナ・ズボフ, 2021)
*6:スチュアート・ブランド, 1988
*7:誰がサイバー・エコノミーを統御するのか, 思想としてのパソコン(西垣通, 1997)
*8: The Original Sin of the Internet. And How Blockchain Can Undo It
*9:2020 Trends Report for Entertainment, Media and Technology